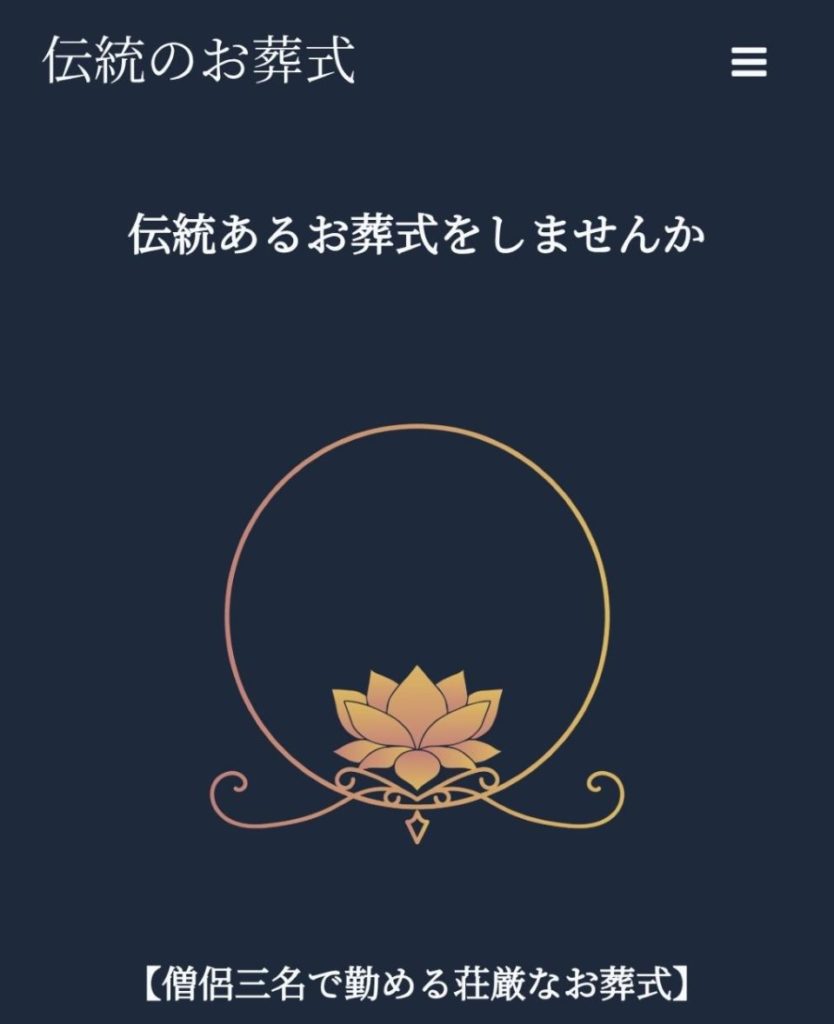お参りのご案内

お参りのご依頼窓口を作成しました

今までのお参りのご案内は下記より
御葬儀
この世にご縁を賜って生まれた命は、いつかはこの世の縁を離れてしまうことでございます。たとえ、それが世の常であるという教えであっても、その悲しみや寂しさというものは耐え難いものです。しかし、そんな中であっても、そこで命は終わりではない、命は人生のその先へ必ず続いてゆくという教えが仏教にはあるのです。
阿弥陀如来という仏様は「人生の先は私にまかせよ」と願われます。その願いの内には私たち一切衆生(すべてのいのち)を救う智慧の力と慈悲の心があります。そして、その救いの力は南無阿弥陀仏のお念仏となり、私たちを極楽浄土へ救ってくださいます。浄土真宗の御葬儀では、そんな阿弥陀如来の智慧と慈悲の救いを聞いていただきながら、ご縁ある命に心を向けてお参りいただきたいと思います。
御葬儀までの流れ
1 まずはお寺にご連絡下さい
まずは光國寺へご連絡下さい。TEL:06-6333-3349 御葬儀・お通夜の日時をご相談させていただきます。 もし、先に葬儀社さまが決まっており日時の候補があるようでしたら、お伝え下さい。
2 葬儀社さまにご連絡下さい
葬儀社さまにご連絡下さい。 お決まりでない場合は、お寺でご紹介、ご相談も承ります。
3 日時を決めたのち 臨終勤行をお勤めします
御当家様、お寺、葬儀社さま、三者相談のうえ日時を決め、その後臨終勤行のお勤めにお伺いします。場所はご自宅・葬儀場どちらでもかまいません。
お勤めのあとは少しお打ち合わせをさせていただきます。(法名、仏壇、過去帳、中陰参り・満中陰の日程等、今後のお参りのことなど)
4 ご親族様やご縁ある方々にご連絡下さい
御縁ある方々にお参りしていただけるように連絡しましょう。
5 お通夜・御葬儀をお勤めします
ひとつひとつ丁寧にお勤めしてまいります。 お念仏・合掌・礼拝・お焼香とともにお参り下さい。
何かご不明なところがある場合は、光國寺へご連絡下さい。(TEL:06-6333-3349)
よくある質問
問: 法名ってなんですか?費用はかかりますか? 答: 法名は「仏弟子としての名前(釋〇〇)」です。 基本的には生前に本願寺で帰敬式を受けて授与されるものですが、生前に授与されていない場合は本願寺御門主に代わり光國寺住職が授与させていただきます。 光國寺では法名料は御葬儀のお布施に含まれていますので、別に用意する必要はありません。 ご希望によって本願寺(本山)に20万円以上の御進納をもって授与される院号法名「〇〇院釋〇〇」というものがあります。
問: 光國寺の御門徒でなくとも、お葬式できますか? 答: はい。もちろんお勤めさせていただきます。檀家・門徒を強制することもございませんので、お参りに心を向けて下さればと思います。
問: 一日葬や直葬でも、お勤めしてくれますか? 答: はい。それぞれの御事情に合わせてお勤めさせていただきます。 ただ、お通夜やお葬儀のお勤めにはそれぞれ意味がありますので、できる限りお勤めされることをお勧めします。
問: お寺なし読経なしのお葬式をしたのですが、やっぱりお経を読んでもらいたいです。あとでお経を読んでもらうことはできますか? 答: はい。たとえば、光國寺の本堂で骨葬という形で法要のお勤めをすることもできます。また法話も聞いていただこうと思います。まずは光國寺までご連絡下さい。 TEL:06-06333-3349

御法事
御法事は年忌法要ともいいます。年忌法要とは先立ちお浄土へ往生された方を想いながら阿弥陀如来のお慈悲の心に照らされていることを聞き、ゆかりある御縁と共に年忌に合わせてお参りをしていただく法要です。
法事・年忌法要は主に一周忌、三回忌、七回忌、十三回忌、十七回忌、(二十三回忌)、二十五回忌、(二十七回忌)、三十三回忌、五十回忌、百回忌の年次でお勤めします。
法要は光國寺の本堂でもお参りいただけます。(本堂使用懇志2万円~)

御法事の流れ
お電話にて日程の調整など打ち合わせをさせていただきますでの、法要の希望日が決まりましたら光國寺までご連絡下さい。(予定が重なる場合もありますので、できるだけ早めのご連絡をお勧めします。) もし、年忌にあたる年かどうかわからない場合もご命日よりお調べしますのでご連絡下さい。 TEL:06-6333-3349
よくあるご質問
問: 家で法事をする時、どのように仏壇を準備したらよいでしょうか。 答: まず仏壇のお荘厳ですが、まず前卓(阿弥陀様のいらっしゃる一段下の棚)に打敷(三角形の織布)をお持ちであればお飾り下さい。 仏具は五具足(香炉、火立×2、花立×2)をお持ちならばそれらでお荘厳下さい。五具足の場合は香炉を真ん中に置き、内側より火立、花立の順に左右対称にお荘厳下さい。 仏具が三具足(香炉、火立×1、花立×1)をお持ちであればそちらでも結構です。三具足は香炉を真ん中に置き、向かって左側に花立、右側に火立てをお荘厳下さい。 御仏飯も仏様の前にお供え下さい。 また、お焼香用の香炉セットがあればご準備下さい。
問: お供え物はどうしたらよいですか。 答: 浄土真宗では特別決まったお供え物はありませんが、地域によっては浄土真宗でもお餅をお供えすることもあります。また、ご先祖様・故人様の好きだったもの、思い出のもの、または後で皆様でいただけるものなどをお供え下さればと思います。
問: 本堂で法事をする際に、何を持っていったらいいですか。 答: 光國寺本堂で御法事をされる際の持ち物は、過去帳、御法事の方のお写真、お花、お供え物をご案内しております。お花は御内陣にすでに設えてありますが、別卓にて過去帳、お写真と共にお飾りしますので出来るだけご用意いただくようにご案内しています。お供え物は上記の(問)を参考にして下さればと思います。

その他仏事について
ご命日のお参り
月ごとにご命日の日にちにお参りをする月参りと、ご命日のその日にお参りをする祥月命日のお参りがあります。今までお参りしたことがなく、まず一度お参りをされてみたいという方もどうぞご連絡下さい。
初盆・お盆・お彼岸のお参り
お盆参りは8月13日(盆の入り)~8月16日(盆明け)の間にお参りをします。初盆のお参りは御縁ある方が往生され、満中陰を過ぎたあとに初めて迎えるお盆のお参りです。お盆の時期より早い7月の中旬~8月16日(盆明け)の間にお参りをします。 お彼岸は春と秋にお参りをする仏事です。春分の日、秋分の日より前後3日間の間にお参りをします。それぞれの御縁にお墓やお家の仏壇にお参り下さい。
お仏壇関連の法要
お仏壇をお迎えする時の入仏法要、またお仏壇を終う時の遷仏法要があります。お仏壇の事やお飾りの仕方などもご相談下さい。
お墓関連の法要
お墓を新たに建てる時の建碑法要、お墓に納骨する時の納骨法要、お墓を終う時の遷仏法要があります。またお手伝いいただく業者さまをご紹介することもできます。

仏事に関してのお悩みやご相談も随時受け付けております。 何かお困りの際は光國寺までご連絡ご相談下さい。 TEL:06-6333-3349 光國寺公式ラインからもご相談いただけます。